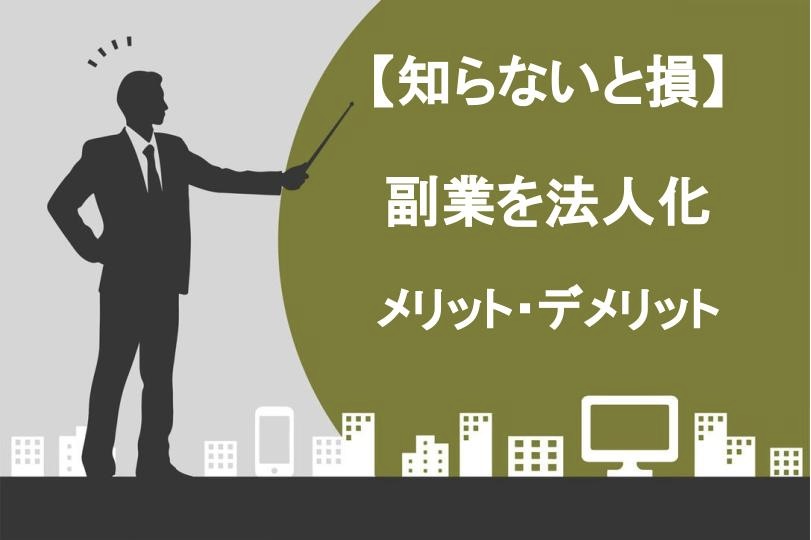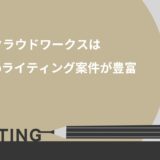「副業で法人化するメリットやデメリットが知りたい」
「法人化するタイミングはいつがいい?」
「法人化の手続きの流れを確認したい」
こんなお悩みにお答えします。
副業収入が増えてくると、負担になるのが税金。手元に残るお金を増やしたくて、副業の法人化を検討している方も多いのではないでしょうか。
ただし、法人化するにあたって毎年の税理士報酬の支払いや副業がバレるリスクがあるので、よく検討してから会社を設立しましょう。あまり考えずに会社を設立すると「思ったよりも節税にならないし、事務作業が増えてしまった……」と、あとで後悔するかもしれません。
そこでこの記事では、以下の内容を解説します。
- 副業を法人化するメリット・デメリット
- 法人化を検討するタイミング
- 法人化するための手順
副業収入が増えたから法人化を検討している方は、ぜひ最後までお読みください。
会社員が副業を法人化する5つのメリット
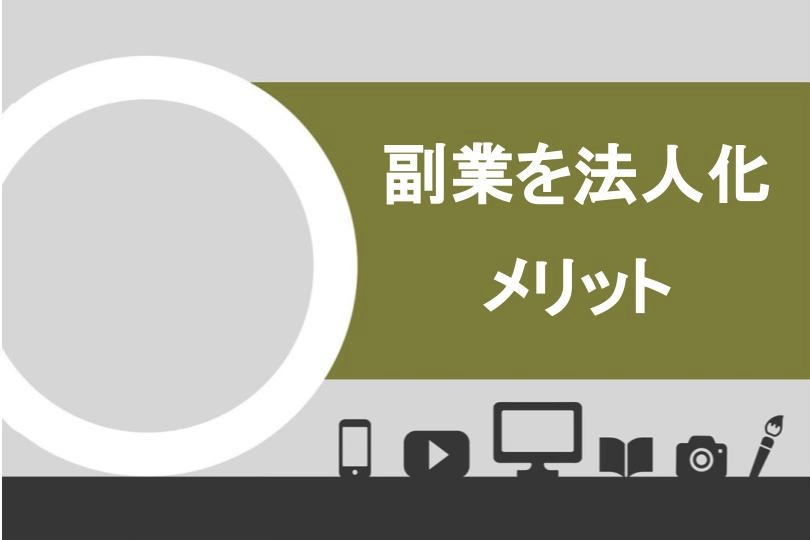
会社員が副業を法人化するメリットは、以下5つのとおりです。
- 節税の種類が増える
- 収入が増えると税率が低くなる
- 収入を分散させることで税金を安くできる
- 社会的信用が高くなる
- 決算月を選べる
それぞれ、順番に解説します。
1. 節税の種類が増える
法人になる最大のメリットは、節税の種類が増えることです。個人事業主のままでも経費は使えますが、法人になると節税できる項目が増えるため、納税額を減らせます。
参考までに以下の項目を経費精算できるため、チェックしてみてください。
- 出張旅費規定:遠方の出張を名目として自分に日当が出せる
- 社宅制度:法人名義で物件を借りることで、家賃の8割以上を経費にできる可能性が高い
- 退職金:自分に退職金を出せる
ほかにも節税につながる制度はあるため、法人化を検討したタイミングで税理士に相談してみるのがおすすめです。
2. 収入が増えると税率が低くなる
副業収入が増えるほど、法人のほうが税率は低くなります。法人税と副業の収入は、経費や控除を引いた課税所得で計算されます。副業収入の場合、年間20万円を超えると所得税と住民税の支払いが必要です。
法人になると法人税のほかに、地方法人税や法人事業税、法人住民税、特別法人税などを支払います。
どちらも課税所得が増えるほど税金は増える点で同じですが、適用される税率が異なります。概算の税率は、以下のとおりです。
- 副業:約15〜60%
- 法人:約22〜35%(実効税率)
個人事業として副業を続けた場合、最大で60%も税金を取られるのは痛いですよね。法人化によって最大税率を下げられるため、収入が増えたタイミングで法人化するのは有効です。
3. 収入を分散させることで税金を安くできる
個人で法人をつくると、自分自身が取締役になり役員報酬として給料を払えます。役員報酬は所得控除の対象です。したがって、法人と役員報酬で収入を分散すれば、納める税金を少なくできます。
具体例をみていきましょう。個人事業主の場合、収入から経費と控除を引いた課税所得が1,000万円であれば、所得税と住民税をあわせて約276万円を税金として納める必要があります。
つぎに、法人化したケースで考えます。課税所得1,000万円を法人400万円と役員報酬600万円に分けると、以下税負担のとおりです。
- 法人:約88万円(実効税率22%で計算)
- 個人:約77.25万円
合計で約165.25万円になるため、個人事業主のままでいるときより約100万の節税につながりました。法人と役員報酬で収入を分散させると税金を安くできるかもしれないので、収益が増えたタイミングで税理士に相談してみてください。
4. 社会的信用が高くなる
法人化する4つ目のメリットは、社会的信用が高くなる点です。個人事業主として活動していると、法人しか取引できないクライアントが存在します。
大きな契約が見込まれるなら、失注をさけるために法人化するのも1つの手段です。また、銀行から融資を受けるときは法人のほうが社会的信用度は高いため、副業より借り入れしやすくなります。
社会的な信用が必要になったタイミングで法人化を検討してみてください。
5. 決算月を選べる
法人化する最後のメリットは、決算月を選べることです。個人事業主の場合、毎年の2月16日〜3月15日の期間で確定申告が必要です。
本業や副業の繁忙期と重なっている場合、確定申告の事務作業があると休みなく仕事をしなければいけません。一方、繁忙期を避けて決算月を指定すれば、業務負担を分散できます。
会社員が副業を法人化する4つのデメリット
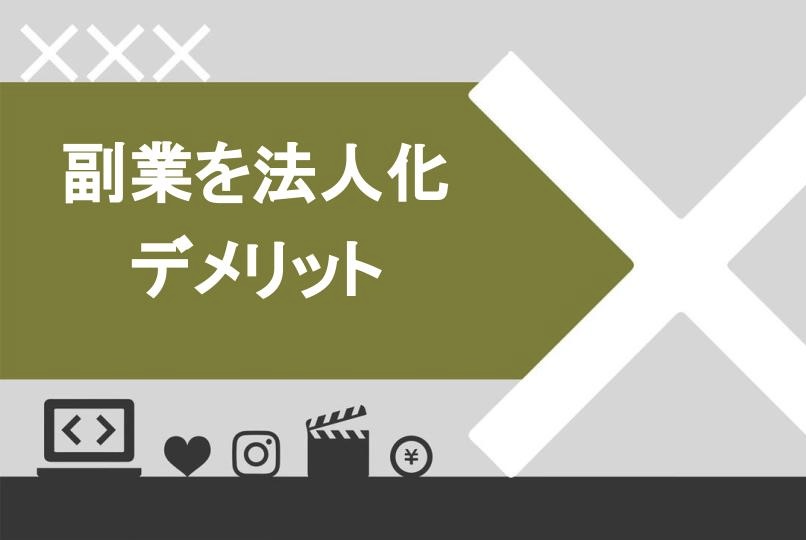
副業を法人化するデメリットは、以下4つのとおりです。
- 設立費用がかかる
- 税理士費用が発生する
- 副業がバレるリスクが高まる
- 赤字でも税金が発生する
それぞれ順番に解説します。
1. 設立費用がかかる
法人を立ち上げるには登記が必要になるため、登録料がかかります。株式会社か合同会社によって金額は異なりますが、概算で以下の費用がかかります。
- 株式会社:25万円〜
- 合同会社:10万円〜
また、法人設立の際には、資本金が必要です。副業の業種にもよりますが、法人用の銀行口座を開設するために最低でも100万円は用意しましょう。
会社設立には初期費用がかかるため、法人化を検討するタイミングでまとまった現金が必要になると心得ておきましょう。
2. 税理士費用が発生する
法人化するにあたって決算処理が複雑になるので、税理士費用が発生します。法人化すると決算書を作成する必要がありますが、20枚以上の申告書を作成しなければいけないため、個人で申請するのは困難です。
税金の知識のない個人が決算書を作成するのは難しいため、プロである税理士に依頼します。なお、業種にもよりますが、年間20〜50万円前後の税理士費用が発生します。
副業のときより決算処理が複雑になるため、税理士費用が発生すると考えておきましょう。
3. 副業がバレるリスクが高まる
法人化することで、会社に副業がバレるかもしれません。法人で役員報酬を支払うと、社会保険料の金額が増えるからです。
会社の経理部門が源泉徴収票を見たとき、社会保険料の支払いが増えたことで副業がバレるケースがあります。
副業を法人化しても独立する予定のない方は、会社にバレるかもしれないと心得ておいてください。
4. 赤字でも税金が発生する
法人になると法人住民税の支払い義務が発生するため、赤字でも7万円ほど納税する必要があります。一方で、副業が赤字の場合、個人事業主であれば納税の義務はありません。
副業の利益があまり出ていない方は、個人事業主のまま活動したほうが税負担は少なくてすみます。
副業を法人化したほうがいい2つのタイミング
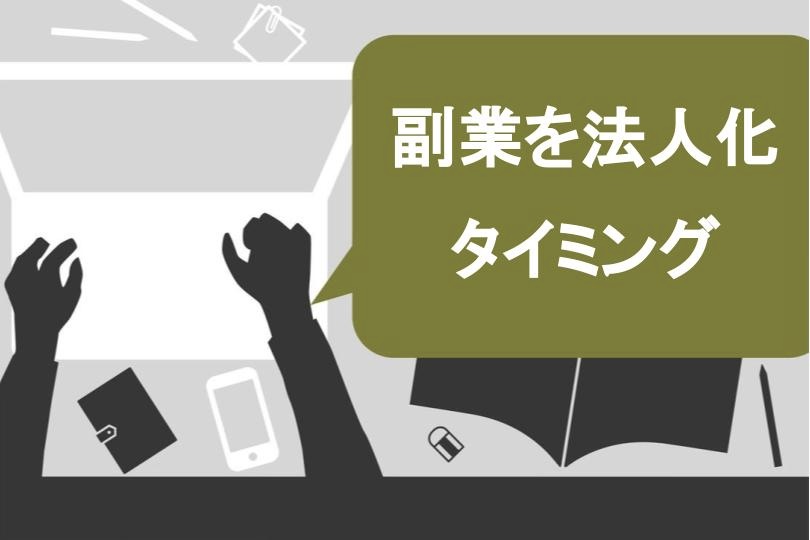
副業を法人化したほうがいいタイミングについては、以下2つのケースが考えられます。
- 副業の課税所得が900万円を超えたタイミング
- 社会的信用が必要になるタイミング
それぞれ順番に解説します。
1. 副業の課税所得が900万円を超えたタイミング
副業の課税所得が900万円を超えたら、法人化を検討しましょう。収入が増えれば増えるほど、所得税の負担が大きくなるからです。所得税の課税金額については、以下の表を参考にしてください。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
引用:国税庁「No.2260 所得税の税率」
課税所得が900万円以上になると、税率が33%と高くなるため、法人化したほうが税金を少なくできます。ただし、法人化することで節税できる項目が増えるため、課税所得900万円未満でも会社を設立したほうが手取り収入を増やせるかもしれません。
副業収入が増えたタイミングで税理士に相談してみると、法人になったほうが税制面でお得になるかが判断できます。
2. 社会的な信用が必要になるタイミング
副業収入が節税面で有利にならなくても、社会的な信用が必要になったタイミングで法人化を検討してみてください。
具体的には、銀行から融資を受けたいときや、クライアントとの取引において法人でないと契約できないときです。事業資金をもとにビジネスを拡大させたいときは、リスクを取ってでも法人化したほうが良いケースもあります。
法人化することで収入を増やせると判断したときは、会社設立を検討しましょう。
副業を法人化する7つの手順

ここまで副業を法人化するメリットやデメリット、会社設立のタイミングについて解説しました。こちらでは、会社設立に踏み切る決断をした方に向けて、法人化する手順を以下7つの順番で解説します。
- 事前準備
- 定款の作成
- 定款の認証
- 資本金の準備
- 登記書類の準備
- 登記申請
- 税務署へ届出
それぞれ順番にみていきます。
1. 事前準備
最初に、会社の基本項目を決めます。全部で6項目あるので、重要な点に絞って解説します。
- 会社の形態(株式会社・合同会社)
- 社名
- 事業目的
- 会社の住所
- 設立日
- 資本金
会社の形態では、株式会社か合同会社にするかを決めます。個人でコストを抑えたいなら合同会社を選んでください。社会的信用を重視したい方や上場・ベンチャーキャピタルを視野に入れている方は、株式会社を選びましょう。
また、資本金は法人用口座を開設するために、100万円は準備するようにしてください。
2. 定款の作成
事前準備が終わったら、定款を作成します。定款とは会社の基本情報や規則が記載された書類のことです。事前準備で考えた基本項目の内容を書類に記載していきます。
法務局の公式ホームページで定款の書式をダウンロードできるため、こちらの用紙を参考にしてみてください。
なお、定款は書類か電子で作成するかを選べます。書類の場合、印紙代の4万円がかかりますが、手続きは電子定款に比べ簡単です。電子定款の場合、印紙代はかかりませんが、電子署名や電子定款を公正役場へ送るなど専門家でないと難しい手続きが必要です。
電子定款で作成する場合、行政書士に依頼したり代行サービス・free会社設立を利用したりするケースが多くなります。定款を作成する際は、書類か電子にするかを決めましょう。
3. 定款の認証
作成した定款は、公証役場で認証を受ける必要があります。公証役場で認証を受けた定款は自由に変更できないため、記入漏れがないか慎重に確認してください。
なお、電子定款で作成したとしても、直接役場に行って書類を受け取る必要があります。
4. 資本金の準備
つぎは、資本金の準備をすすめます。法人用口座はないので、個人の口座に資本金を振り込みましょう。
資本金は1円から準備できますが、あまりに少ない金額だと会社の信用度にかかわります。会社設立後の法人用口座を開設するため、100万円は入金するようにしましょう。
5. 登記書類の準備
つぎに、登記書類を準備します。登記に必要な書類は、以下のとおりです。
- 登記申請書
- 登録免許税分の収入印紙を貼り付けた用紙
- 定款
- 発起人の決定書
- 取締役の就任承諾書
- 代表取締役の就任承諾書
- 監査役の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書
- 資本金の払い込みを証明する書類
- 印鑑届出書
- 登記すべきことを保存したCD-R
登記申請には必要書類が多く手間がかかるため、余裕のない方は司法書士への依頼を検討してみてください。
6. 登記申請
登記書類を揃えたら、法務局で申請します。審査には7〜10日ほどかかり、法人登記が認められると、ようやく会社を設立できます。
登記が完了すると「登記事項証明書」と「印鑑証明書」を取得できるため、法務局で受け取るか、オンラインで入手しましょう。
7. 税務署へ届出
会社設立が完了したら、お住まいの税務署に「法人設立届出書」と「青色申告の承認申請書」を提出します。
法人設立の届出書は会社設立の2ヶ月以内に提出する必要があります。期限に遅れないように書類を提出しましょう。
起業したい方必見!ビジネスモデルの組み方を解説
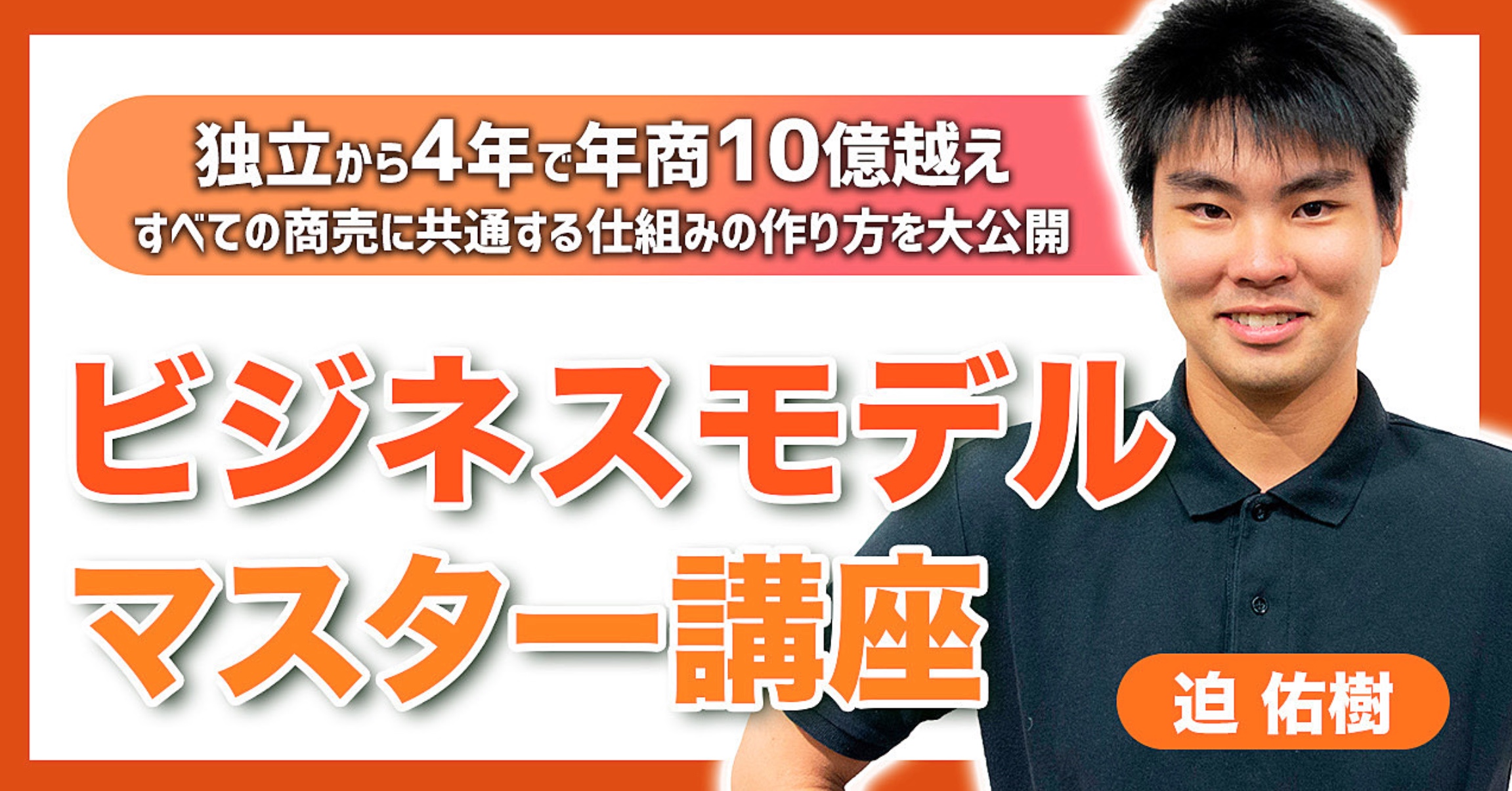
迫さんのBrain【ビジネスモデルマスター講座】全ての商売に共通する仕組みの作り方を大公開では、会社設立から2年で年商10億円に到達したビジネスモデルの設計法を徹底解説しています。
- ビジネスモデルの基礎知識
- ビジネスを組む具体的な10のフロー
- 4つのビジネスモデルの構築事例
- 具体的なビジネスへの活用方法
現役経営者が実際にビジネスモデルを組んだ手段や思考について、余すことなく紹介しています。
- 副業の収入をさらに伸ばしたい
- 現役経営者の思考や具体的手法を学びたい
- ビジネスモデルを構築して労力をかけずに事業を回したい
と考えている方には、必見の内容です!
以下のボタンから詳細を確認できるので、ぜひチェックしてみてください。