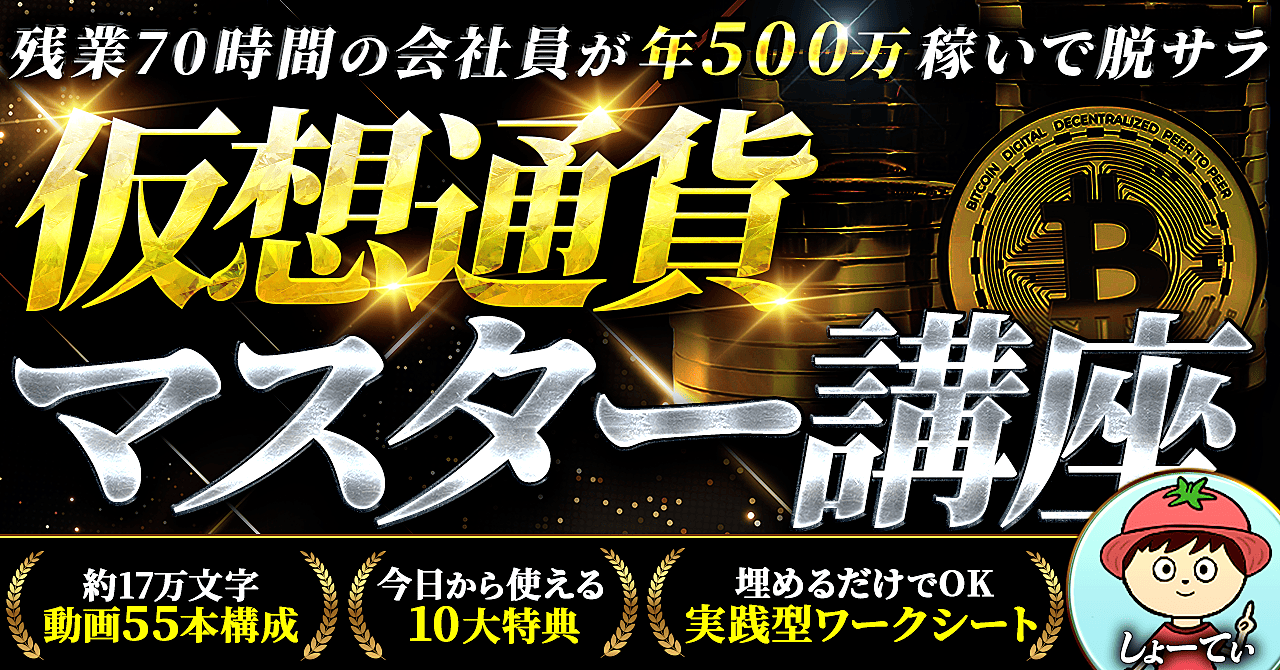Brainメディア運営部です!
今回の記事は、1年間で1,863人が受講した「仮想通貨マスター講座」で大人気のしょーてぃさんから情報を提供していただき記事を作成させていただきました。
簡単にしょーてぃさんの紹介をさせていただきます。

今回の記事では、仮想通貨の専門家であるしょーてぃさんの知見をもとに、
今知っておかないと時代に取り残される〝ステーブルコイン〟の全貌を解説します。
「仮想通貨って儲かるかもしれないけど、
値動きが激しすぎて怖い…」
そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
事実、ビットコインやイーサリアムのような主要通貨は価格の上下が大きく、
日常の決済や資産の避難先としては不便です。
そこで注目されているのが、ドルや円とほぼ同じ価格を保つ〝ステーブルコイン〟。
この仕組みを理解して使いこなせれば、
世界中への送金や資産保全、
仮想通貨サービスの活用まで、可能性が一気に広がります。
しかし、多くの人はそのメリットだけでなく、
危険性や種類の違いまでは知りません。
知らずに扱えば、粗悪なコインをつかまされて
価値がゼロになるリスクも現実に存在します。
2022年に起きたUST崩壊事件は、その典型例です。
正しい知識があれば避けられる損失も、
無知のままだと一瞬で資産を奪い去られます。
本記事では、ステーブルコインと電子マネーの違い、
注目される理由、利用時のリスク、3つのタイプ別の仕組み、
そして入手方法までを網羅的に解説。
初心者でも分かるように具体例を交えながら、
仮想通貨の新しい世界の入り口を案内します。
この記事を読み終えたとき、あなたはステーブルコインを
安全かつ戦略的に活用できる状態になっているはずです。
今のうちに基礎を固めて、
未来のチャンスを掴み損ねないようにしましょう。
目次
ステーブルコインとは?初心者でも理解できる基本と仕組み
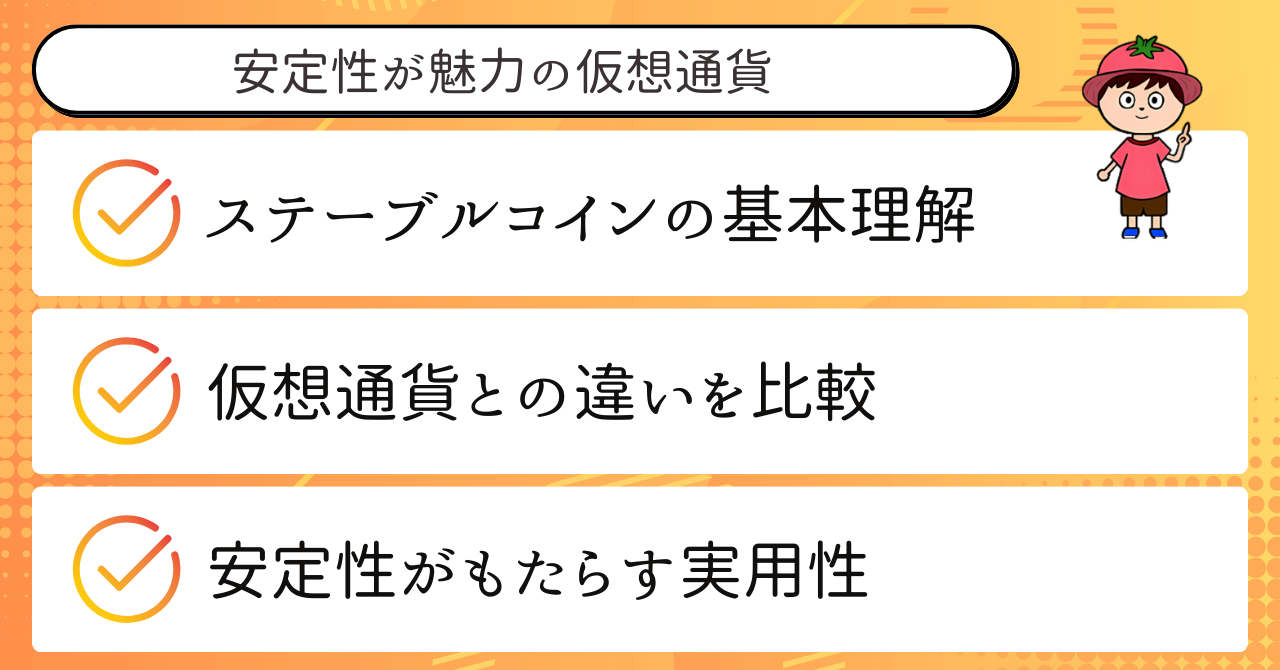
仮想通貨の世界において〝ステーブルコイン〟は、
知っているかどうかで活用の幅が大きく変わる存在です。
その名の通り、価格が安定(ステーブル)したコインであり、
米ドルや日本円とほぼ同じ価値を保つことを目的としています。
たとえばUSDTやUSDC、DAIといった有名な銘柄は、
常に1ドル前後の価格を維持するように設計されています。
この仕組みのおかげで、日常の決済や海外送金、
資産の避難先として非常に便利です。
従来のビットコインやイーサリアムは価格変動が激しく、
日ごとに価値が上下してしまうため決済には不向きでした。
Nintendo Switchを買いに行ったら、
昨日は0.02BTCだったのに今日は0.03BTCになっている。
そんな変動では、安定した取引は難しいのです。
この欠点を補うために誕生したのがステーブルコインです。
価値が安定しているため、仮想通貨決済や資産運用の中で
〝現金のように使える〟役割を果たします。
ただし、便利さの裏には仕組みへの理解が不可欠です。
なぜ価格が安定しているのか、その背景を知らずに使うと
大きな損失を被る可能性があります。
ステーブルコインの定義と成り立ち
ステーブルコインは、法定通貨や貴金属などと価値を連動させるよう設計された仮想通貨の総称です。
ドルや円、金・銀・プラチナなど、
裏付けとなる資産と同等の価値を保つための仕組みが組み込まれています。
発行の方法や担保資産はプロジェクトによって異なりますが、
共通しているのは〝価値の安定〟を最優先している点です。
価格が安定していることで、他の仮想通貨と違い、
送金や決済での安心感が圧倒的に高まります。
たとえば、1USDCの裏には必ず1ドルが存在するよう担保されており、
いつでも等価交換できるようになっています。
この担保構造があるからこそ、
為替のような急な変動を気にせず利用できるのです。
また、旅行先で宿泊費を支払う場合も、
価格が安定しているステーブルコインなら現地通貨への両替を気にせずに使えます。
海外のホテルやオンライン決済でも、
〝1USDC=約1ドル〟という感覚で支払えるのは大きな利点です。
こうした仕組みによって、仮想通貨の持つ「インターネット上での直接送金」という利便性と、
法定通貨の「価値の安定性」を融合させた存在が、ステーブルコインといえます。
このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。
- ステーブルコインは法定通貨や貴金属と価値を連動させる仮想通貨
- 担保構造により価格をほぼ一定に保てる
- 国際送金や海外決済でも為替変動を気にせず利用できる
価値の安定性と仮想通貨の利便性を兼ね備えたステーブルコインは、
今後さらに利用シーンが拡大していくでしょう。
価格変動が激しい仮想通貨との違い
仮想通貨と聞くと、多くの人がまず思い浮かべるのはビットコインやイーサリアムです。
しかし、これらは価格変動が激しく、
日単位、時には数時間で価値が大きく上下します。
例えば、昨日1BTC=400万円だったものが、
今日には420万円、あるいは380万円に変動することは珍しくありません。
この大きなボラティリティは投資対象としては魅力ですが、
日常の決済手段としては不向きです。
ステーブルコインは、この不安定さを解消するために誕生しました。
ドルや円などの法定通貨と価値を連動させることで、
価格の変動幅を極小化しています。
仮にNintendo Switchを購入する場面を想像してみましょう。
ビットコインでの支払いだと、昨日は0.02BTCだった価格が、
今日は0.03BTCになる可能性があります。
この差は数千円規模になり、消費者も店舗側も安定した取引ができません。
一方で、1USDC=約1ドルであれば、
昨日も今日もほぼ同じ価格で支払い可能です。
そのため、ステーブルコインは実用的な決済手段として
世界中で採用が広がっています。
また、投資家にとっても価格が一定であることは重要です。
急な相場変動時に資産を避難させる〝安全な待機場所〟として活用できるからです。
実際に多くのトレーダーは、仮想通貨の暴落局面で
資産をUSDTやUSDCに切り替え、価値を守っています。
これにより、再び相場が落ち着いたタイミングで、
次の投資チャンスにすぐ動けるわけです。
ここまでの違いを理解しておくことで、
ステーブルコインをより戦略的に使いこなせるようになります。
一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。
- ビットコインやイーサリアムは価格変動が激しい
- ステーブルコインは法定通貨連動で価格が安定
- 決済や資産保全に実用的で、投資戦略にも有効
投資と決済、それぞれの目的に合わせて仮想通貨を選ぶことが、
資産を守り増やす第一歩です。
日常決済を変える〝価格安定〟の魅力
ステーブルコインの最大の強みは、
その価格安定性が日常決済に革命をもたらすことです。
現金やクレジットカードと同じ感覚で使える仮想通貨として、
世界中で採用が広がっています。
例えば、海外旅行先でホテル代や食事代を支払うとき、
ステーブルコインなら為替変動を気にせずに支払いできます。
1USDC=約1ドルという安定した価値があるため、
現地通貨に両替する必要がなく、手数料も最小限に抑えられます。
これは特に、インフレ率が高く通貨価値が日々下がる国では大きなメリットです。
現地通貨よりもステーブルコインでの受け取りを希望する
店舗やフリーランサーが増えています。
また、オンラインショッピングでも同様です。
海外のECサイトで商品を購入する際、
クレジットカード決済だと為替手数料や反映までの時間がかかりますが、
ステーブルコイン決済なら数分で完了します。
さらに、ステーブルコインはブロックチェーン上で直接やり取りされるため、
銀行の営業時間や国境の制限を受けません。
日曜夜でも祝日でも、いつでも取引可能です。
実例として、フリーランスのデザイナーが海外クライアントから報酬を受け取る場合、
従来は国際送金で数日かかっていたものが、ステーブルコインなら数分で着金します。
このスピード感と低コストは、
国際的な仕事の幅を広げる大きな武器となります。
このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。
- 価格安定により日常決済や海外送金での安心感が高い
- 両替や為替手数料を削減できる
- ブロックチェーン送金は24時間365日利用可能
ステーブルコインは、仮想通貨を〝投資対象〟から
〝生活の道具〟へと進化させる存在だと言えるでしょう。

日常の買い物や海外送金でストレスをなくせるのが、
ステーブルコインの面白さなんですよ!
ステーブルコインと電子マネーの本質的な違い
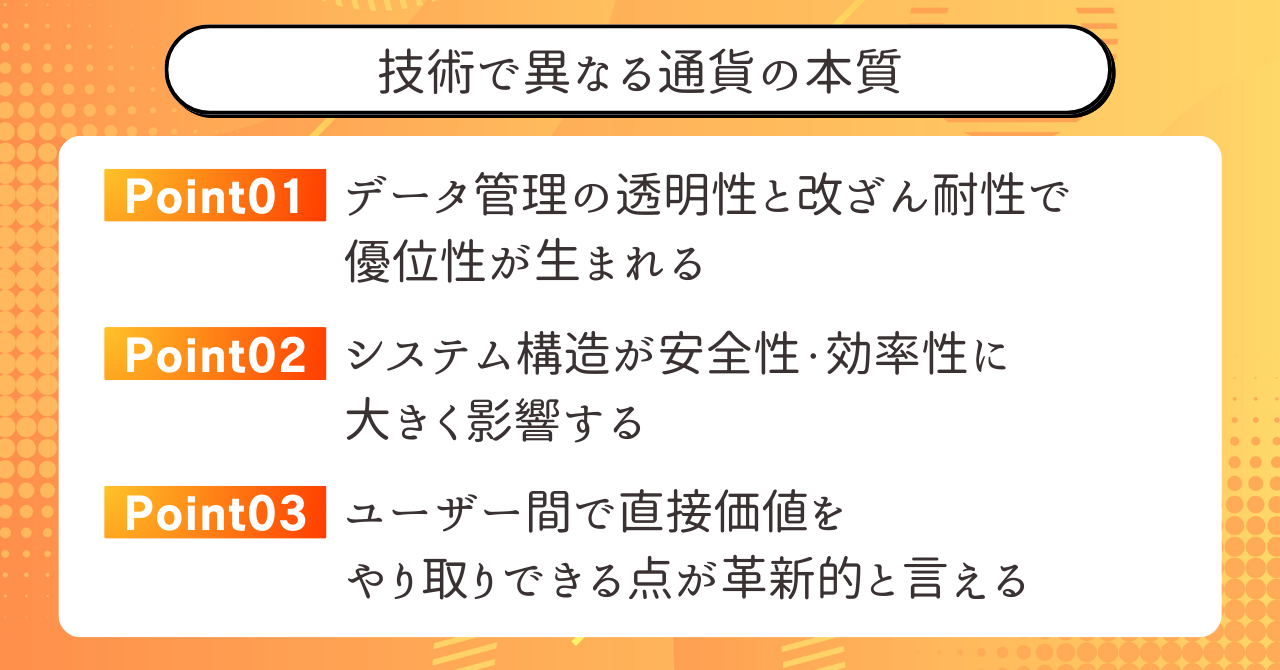
ステーブルコインは「ドルや円と同じ価値を保つ仮想通貨」、
電子マネーは「運営会社が発行・管理するデジタル通貨」という違いがあります。
一見すると似ていますが、その根本的な仕組みや利用可能な場面は大きく異なります。
この章では、その本質的な差を3つの視点から解説し、
なぜステーブルコインが次世代の送金手段と呼ばれるのかを理解できるようにします。
ブロックチェーン技術の有無がもたらす差
ステーブルコインと電子マネーの最大の違いは、
基盤となる技術にあります。
ステーブルコインはブロックチェーン上で発行され、
取引記録が分散管理されます。
これにより、誰か一人や特定の企業がデータを改ざんすることは極めて困難です。
一方、電子マネーは発行会社が一括管理する中央集権型システムです。
例えばSuicaやPayPayは、必ず運営会社が間に入り、
決済や残高管理を行っています。
このため、送金の可否や上限、利用可能地域なども運営側の判断に依存します。
具体例として、フリーランスのデザイナーが海外クライアントから報酬を受け取る場合を考えましょう。
PayPayでは国境を越えた直接送金はできませんが、
ステーブルコインなら世界中のユーザーから即時に受け取ることが可能です。
しかも取引は24時間365日稼働します。
この技術的な違いこそが、ステーブルコインを単なる「電子マネーの代替」ではなく、
新しい金融インフラとして位置づけています。
このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。
- ステーブルコインはブロックチェーン上で発行・管理される
- 電子マネーは発行会社による中央集権管理が必要
- 国境を越えた直接送金が可能で24時間稼働
中央管理型決済と分散型送金の比較
電子マネーの多くは「中央管理型決済システム」を採用しています。
これは必ず運営企業が介入し、全ての取引を承認・記録する方式です。
SuicaやPayPayなどが典型で、送金や残高管理は企業サーバーで行われ、
利用範囲や条件はその企業が決定します。
これに対し、ステーブルコインは「分散型送金」が可能です。
ブロックチェーン上で取引が記録され、世界中のノードが分散管理するため、
取引の承認や履歴保存はネットワーク全体で行われます。
つまり、企業や特定の管理者を介さずに、
ユーザー同士で直接お金を送受信できるのです。
例えば、あなたが海外の知人に送金する場合、
銀行送金では数日かかり、手数料も数千円単位が一般的です。
一方、ステーブルコインを使えば、数分〜数十秒で着金し、
手数料も数円〜数十円程度に抑えられます。
これは中央集権的な制限や高コストを排した、分散型ならではの強みです。
この違いは、国際的なビジネスや個人間送金の場面で
特に大きな差となって表れます。
このパートで押さえるべきポイントは次の3つです。
- 中央管理型は企業が全ての決済を管理・承認
- 分散型送金はブロックチェーン上で直接取引可能
- 海外送金では速度・コストともに分散型が有利
ユーザー間で直接送金できる革命的仕組み
ステーブルコインの真価は、
世界中のユーザー同士が直接お金をやり取りできる点にあります。
これは従来の銀行や電子マネーにはなかった革新的な仕組みです。
従来の決済では必ず第三者(銀行・企業)が介入し、
その承認を経ないと取引が成立しませんでした。
しかしステーブルコインでは、ブロックチェーン技術により
送金者と受取人がネットワーク上で直接接続されます。
送金内容は暗号化され、全ノードに分散して記録されるため、
改ざんや二重送金が極めて困難です。
これにより、信頼関係のない相手とも安全に送金できます。
例えば、フリーランスのデザイナーが海外のクライアントから報酬を受け取る場合、
従来はPayPalや銀行送金を通して数日待つ必要がありました。
手数料も数%取られます。
しかしステーブルコインを使えば、数分で着金し、手数料も数十円程度で済みます。
まさに時代を変える送金方法と言えるでしょう。
この仕組みにより、国境を超えた個人間取引やマイクロペイメント(小額決済)が現実的になり、
経済活動のスピードが一気に加速します。
このパートで押さえるべきポイントは次の3つです。
- 第三者不要でユーザー同士が直接送金可能
- 暗号化と分散管理で高い安全性を確保
- 国際送金や小額決済が低コスト・高速化

中央管理者が不要になるって、ほんと革命的!
個人間で直接やり取りできる自由度は、
一度体験すると戻れなくなるよ。
BTCとETHの仕組みや用途の違いを丁寧に解説し、「なぜステーブルコインが別枠で必要なのか」理解を深めるべき読者向けの記事です。
【初心者必見】ビットコインとイーサリアムの違いとは?失敗しない選び方と買い方を徹底解説!
なぜ今ステーブルコインが注目されるのか【メリット】
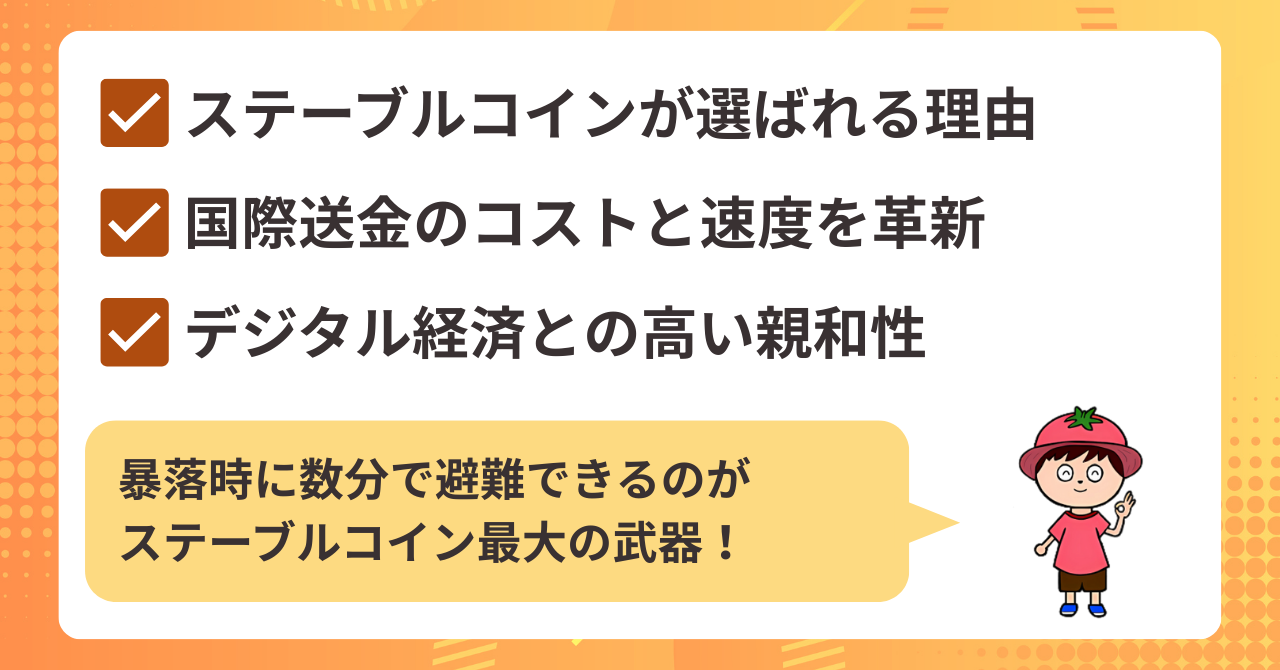
ステーブルコインは単なる「価格が安定した仮想通貨」ではなく、
世界の金融インフラを変える可能性を秘めた存在です。
国際送金の高速化、DeFiやブロックチェーンゲームへの即時利用、
そして暴落時の資産退避など、その用途は多岐にわたります。
特に、銀行や電子マネーでは不可能だったスピードと低コストを両立できる点が、
世界中の投資家や開発者から熱い注目を集めています。
世界中への送金を低コスト・高速で実現
ステーブルコインの最大の強みのひとつが、
世界中のどこへでも瞬時に送金できる点です。
従来の国際送金は、銀行や送金業者を経由するため数日かかり、
手数料も高額でした。
さらに、国や地域によっては送金自体が制限される場合もあります。
一方でステーブルコインなら、ブロックチェーンを通じて数分以内に着金し、
手数料も数十円〜数百円程度と格安です。
例えば、日本のフリーランスエンジニアがブラジルのクライアントから報酬を受け取る場合、
銀行送金では着金まで4日以上かかり、手数料も5000円近く必要ですが、
ステーブルコインなら数分・数十円で完了します。
このスピードとコスト削減は、国際的なビジネスや個人間の取引を加速させ、
世界経済のボーダーレス化を後押しします。
このパートで押さえるべきポイントは次の3つです。
- 国際送金が数分以内で完了する
- 手数料が数十円〜数百円と格安
- 地域や国の制限を受けにくい
DeFi・ブロックチェーンゲームでの即時活用
ステーブルコインは、DeFi(分散型金融)やブロックチェーンゲームといった
新しい仮想通貨サービスで即座に利用できます。
銀行や電子マネーでは口座との接続や両替の手続きが必要ですが、
ステーブルコインはそのままウォレットから接続して使えるため、
スピードと利便性が段違いです。
例えば、PancakeSwapなどのDeFiサービスでは、
USDCやDAIなどのステーブルコインを預けるだけで年利数%の利息が得られます。
ゲーム分野でも、NFTアイテムの売買や対戦の報酬受け取りに直接ステーブルコインが使えるため、
即時に利益を確定させられます。
さらに、価格が安定しているため、
ビットコインやイーサリアムのように価値が大きく変動するリスクを避けながら運用できるのも魅力です。
このパートで押さえるべきポイントは次の3つです。
- DeFiで即時に資金を運用できる
- ブロックチェーンゲーム内の決済がスムーズ
- 価格変動リスクを抑えつつ活用可能
暴落時に他通貨へ瞬時に避難できる安全性
ステーブルコインは、仮想通貨市場が急落した際の
避難先としても非常に優秀です。
ビットコインやイーサリアムなどの価格変動が激しい通貨を直接日本円やドルに戻そうとすると、
取引所を経由する時間や手数料がかかり、暴落スピードに追いつけないことがあります。
しかし、DeFiや海外取引所であれば、
保有する通貨をその場でステーブルコインに交換できるため、
数分で資産を安全な価値に移すことが可能です。
例えば、海外取引所でETHが急落を始めたとき、
USDCに変える操作は数クリックで完了し、その間に大幅下落を回避できます。
さらに、同じプラットフォーム内で完結するため、
送金待ちや銀行営業時間に左右されないのも大きな利点です。
こうした即時避難の仕組みを理解しておくことで、
相場の変動による大きな損失を防げます。
特に、24時間365日動く仮想通貨市場では、
このスピード感が資産保全の成否を分けます。
このパートで押さえるべきポイントは次の3つです。
- 市場暴落時の資産避難が即時可能
- 法定通貨よりも交換がスピーディー
- 大きな損失を回避しやすい

「暴落時に“数分で避難”できるのがステーブルコイン最大の武器!
これ知らないと本当に危険です!」
ステーブルコイン利用時の注意点とリスク
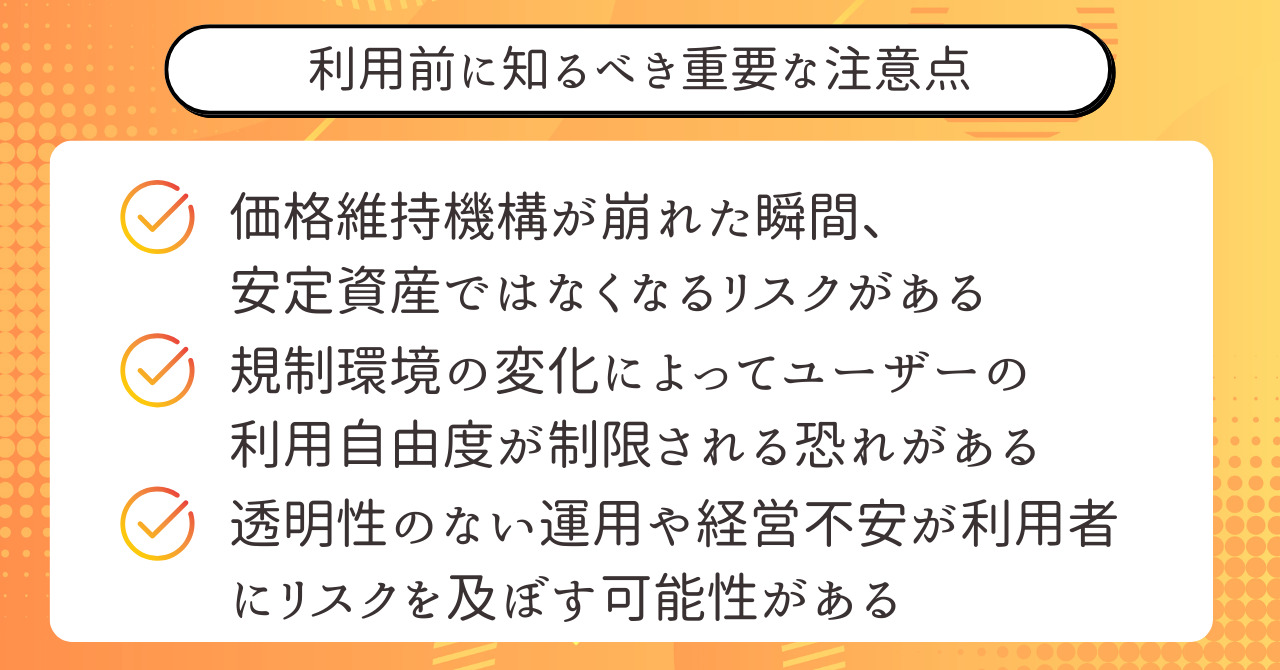
どれだけ便利で魅力的に見える金融ツールでも、
必ず裏にはリスクが潜んでいます。
ステーブルコインも例外ではなく、価格維持システムの破綻や規制強化、
中央集権化による信頼依存など、知っておくべき落とし穴があります。
特に、知識不足のまま高利回りだけに惹かれて利用すると、
大切な資産を一瞬で失う危険性があります。
この章では、利用前に必ず理解しておくべき3つの主要リスクを解説します。
価格維持システムが崩れる可能性
ステーブルコインは「常に1ドルと同じ価値を保つ」という性質が最大の特徴ですが、
それを支える仕組みが崩れれば、その安定性は一瞬で失われます。
価格の裏付けとなる資産やアルゴリズムが破綻すると、
価値が急落し、最悪の場合はほぼ無価値になることもあります。
これは、安定していると思っていた足場が突然抜け落ちるようなものです。
例えば、2022年5月にはアルゴリズム型のステーブルコイン「UST」が、
担保となるLUNAの暴落に伴い価格維持に失敗し、
短期間で1ドルから0.1ドル未満まで下落しました。
この出来事は多くの投資家に大きな損失をもたらし、
ステーブルコインのリスクを強く印象付けました。
投資家の中には、数千万円単位の資産を数日で失ったケースも報告されています。
法定通貨担保型であっても、発行元企業が保有資産をリスクの高い運用に回していた場合、
その運用失敗が即座に価格崩壊につながる危険性があります。
さらに、小規模かつ無名の発行体では資産証明の透明性が低く、
不安定要素が多いのが現実です。
したがって、ステーブルコインを選ぶ際には、
担保の種類や管理体制を必ず確認することが重要です。
このパートの要点は次の3つです。
- 価格安定は仕組みに依存している
- 過去に破綻例(UST事件)がある
- 担保や発行元の信頼性を事前確認すべき
規制強化や法的リスクの影響
ステーブルコインは、ドルや円など既存の法定通貨と価値を連動させているため、
国や政府の金融システムに深く関わります。
このため、規制強化や法改正の影響を受けやすい資産クラスです。
特に、通貨の発行は国家の重要な権限であり、
無許可での発行や運営は「通貨の信用を損なう行為」とみなされる可能性があります。
実際、日本では偽札作成が3年以上の懲役刑にあたるほど重い罪です。
過去には、アメリカやEUでステーブルコイン発行者に対する
厳格な監査義務や資産保有ルールの導入が検討され、
規制が強まる傾向が見られました。
例えば、米国の一部議員は「裏付け資産が不透明なステーブルコインは金融システムを脅かす可能性がある」として、
発行停止や使用制限を求める動きを見せています。
このような法的圧力は、マイナーなステーブルコインほど致命的になりやすいのが実情です。
一方で、各国政府もデジタル通貨との共存を模索しており、
中国のデジタル人民元や日本のデジタル円のように、
中央銀行発行のデジタル通貨プロジェクトも進行中です。
そのため、規制リスクはゼロではないものの、
主要銘柄(USDT・USDCなど)については共存路線が取られる可能性が高いと考えられます。
このパートの要点は次の3つです。
- 通貨発行は国家権限に直結するため規制対象になりやすい
- 過去に監査強化や資産ルール導入の動きがあった
- 主要銘柄は規制共存の可能性が高い
中央集権化による信頼依存とその懸念
仮想通貨の原点は「特定の管理者を持たない非中央集権的な通貨を作る」という理念にあります。
しかし、多くのステーブルコインは特定企業や団体が運営する中央集権型であり、
その発行元への信頼が前提となります。
これは、銀行口座を持つのと同じく「運営者が資産を安全に管理してくれる」という
信頼関係が必要になるということです。
もし発行企業が不正運用や倒産、規制違反を起こせば、
コインの価値が維持できなくなり、
保有者が大きな損失を被る可能性があります。
例えば、2022年には一部のマイナーなステーブルコインが
運営破綻によって急落し、価値が数日で90%以上失われた事例がありました。
特に透明性の低い運営元や小規模プロジェクトほど、こうしたリスクは高まります。
そのため、利用する際は発行元の信頼性や財務状況、
資産の運用方針を必ず確認し、
できるだけ時価総額の大きな銘柄(USDT・USDC・DAIなど)に限定することが推奨されます。
このパートの要点は次の3つです。
- 中央集権型は発行元への信頼が前提になる
- 運営破綻や不正で価値が急落する可能性がある
- 主要銘柄を選び信頼性を重視することが重要

リスクは避けられないけど、
ちゃんと信頼できる銘柄を選べば安全性はぐっと高まるよ!
3種類のステーブルコインと仕組みの違い
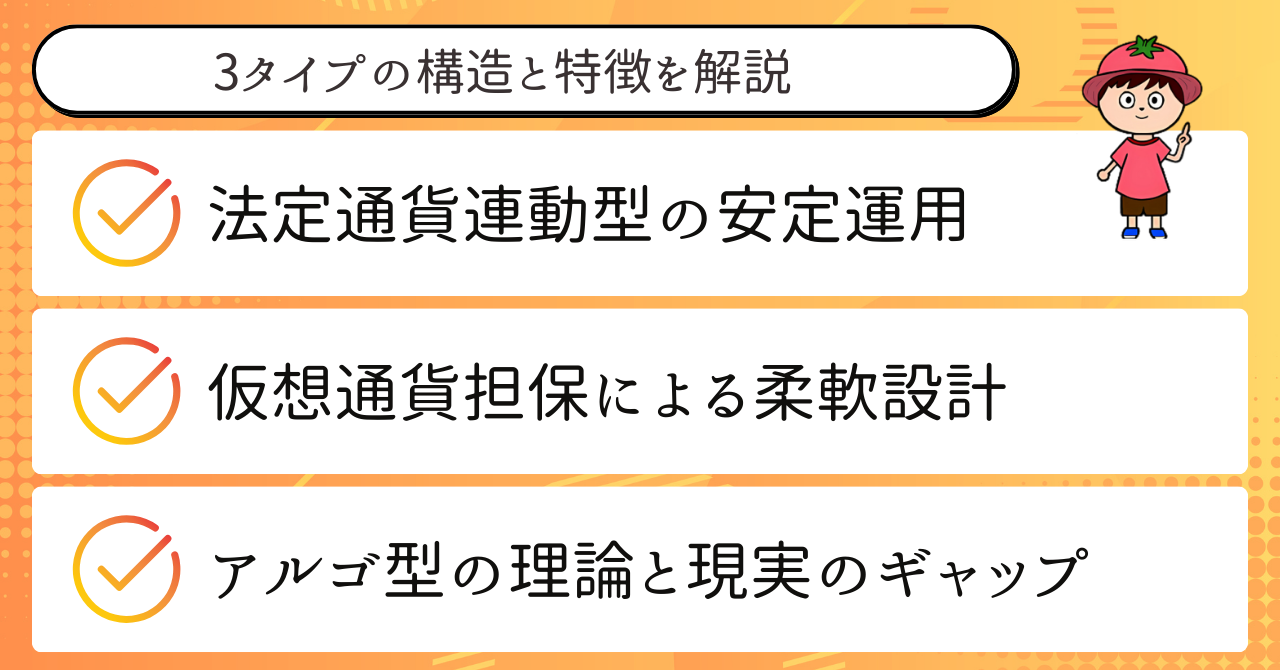
一口にステーブルコインといっても、その価格を安定させる仕組みは
大きく3つに分類されます。
それぞれの方式は、価格の安定性やリスク、利用シーンが異なります。
ここを理解しておくことで、突然の市場変動や不安定なニュースが出た際にも、
自分で安全性を判断できるようになります。
本章では、代表的な3種類のステーブルコインと、
その具体的な仕組みをわかりやすく解説していきます。
法定通貨担保型:安定性と代表的プロジェクト
法定通貨担保型ステーブルコインは、米ドルや円などの法定通貨を裏付け資産として保有し、
その価値を1対1で維持する仕組みを持っています。
発行体は、受け取った法定通貨を銀行口座や国債などの安全資産で管理し、
必要に応じて利用者のコインと交換できるようにします。
このため、理論的には常に同じ価値を保つことが可能です。
代表的な例として、USDT(テザー)やUSDC(USDコイン)、BUSD(バイナンスUSD)があります。
例えばUSDCは、米企業Circle社が発行し、
準備金の大部分を米国債などの低リスク資産で運用しています。
このため、急激な市場変動があっても価値が崩れにくく、
多くの投資家や企業が安心して利用しています。
ただし、発行体の資産運用方針や監査体制が不透明な場合は注意が必要です。
過去には、準備資産が十分でないとの疑惑が浮上し、
市場に不安が広がった事例もありました。
そのため、利用前には発行元の信頼性や透明性を必ず確認することが重要です。
- 法定通貨を担保に価値を安定させる
- 代表例はUSDT・USDC・BUSD
- 発行元の透明性と信頼性を要確認
暗号資産担保型:担保率と資金効率の向上
暗号資産担保型ステーブルコインは、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などの
価格変動のある仮想通貨を担保として預け、その価値を裏付けに発行されます。
代表的なプロジェクトは、分散型組織MakerDAOが運営するDAIです。
ユーザーはETHなどをスマートコントラクトに預け入れ、
その価値の一部をステーブルコインとして引き出せます。
この仕組みでは、価格変動リスクに備えて、
担保率は通常150%以上に設定されています。
たとえば100ドル分のDAIを発行したい場合、
最低でも150ドル分のETHを預けなければなりません。
ETH価格が下落し担保率が基準を下回ると、
自動精算が行われ担保資産が売却されます。
この方式の最大の魅力は、
保有する暗号資産を売却せずに資金を引き出せる点です。
たとえば将来値上がりが期待されるETHを手放さずに、
DAIを得てDeFi運用や別の投資に活用できます。
一方で、市場暴落時には担保精算のリスクがあるため、
常に担保率の確認と管理が必要です。
- 暗号資産を担保に発行されるステーブルコイン
- 担保率は通常150%以上で価格変動に対応
- 保有資産を売らずに資金を活用できるメリット
アルゴリズム型:価格維持の挑戦と失敗事例
アルゴリズム型ステーブルコインは、法定通貨や暗号資産といった担保を持たず、
プログラムの仕組みだけで価格を一定に保とうとする方式です。
供給量を自動で増減させることで1ドルの価値を維持するよう設計されています。
代表例としてUSTやFRAXが知られています。
USTの場合、LUNAという別の仮想通貨と連動し、
USTの価格が下がればLUNAを売ってUSTを買い支える、
逆に価格が上がればUSTを売却するといった仕組みでした。
しかし2022年、LUNAの価格が急落すると買い支え資金が枯渇し、
USTは1ドルを維持できず暴落しました。
この事件は「アルゴリズム型は担保がないため一度信頼を失うと回復が難しい」というリスクを浮き彫りにしました。
アルゴリズム型は中央管理者が不要で、
完全分散型を実現できる可能性がある一方、
価格安定の難易度が非常に高く、
過去の事例では持続的な成功例がほとんど存在しません。
投資や利用の際は、プロジェクトの仕組みや市場状況を十分に理解する必要があります。
- 担保資産なしでプログラムにより価格を維持
- UST崩壊で価格安定の難しさが露呈
- 完全分散型を目指すが持続性に課題あり

アルゴリズム型はロマンがあるけど、
過去の失敗例からもリスクは高め。
初心者は無担保型に手を出す前に、
担保型で慣れておくのがおすすめだよ!
ステーブルコインの入手方法と実践手順
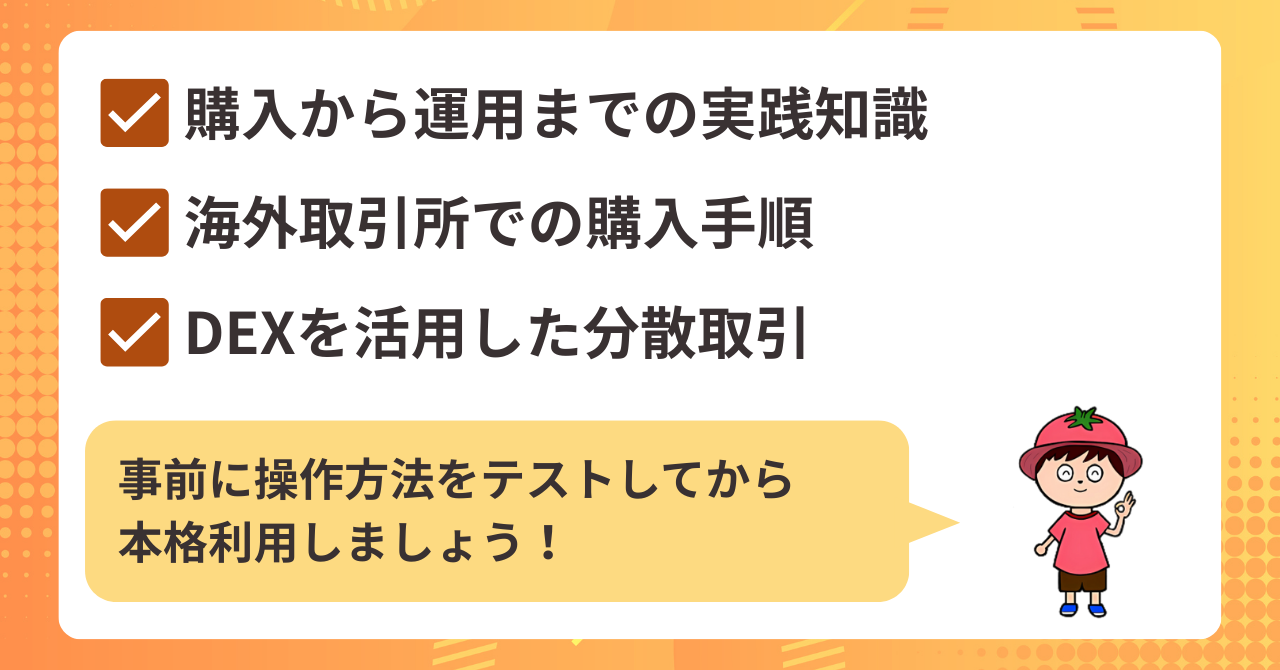
ステーブルコインは知識さえあれば誰でも入手できますが、
国内と海外では取引環境や流れが大きく異なります。
特にDeFiや海外取引所を使いたい場合、
効率的かつ安全な入手手順を理解しておくことが重要です。
この章では、初心者が迷わず実践できる購入ルートや具体的な送金方法、
取引のポイントまで丁寧に解説します。
海外仮想通貨取引所での購入ステップ
海外仮想通貨取引所では、日本円の直接入金ができないため、
まず国内取引所でビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)、XRPなどを購入し、
それを海外取引所へ送金する必要があります。
送金手数料を抑えるためには、GMOコインのように送金無料の取引所を使うか、
手数料の安いXRPを利用するのが一般的です。
送金後は、海外取引所(Bybit、Gate.io、Binanceなど)で受け取った仮想通貨を
USDTやUSDCなどのステーブルコインに交換します。
例えばETHを送った場合、そのままETH/USDCの取引ペアで両替可能です。
実際、ETHを10万円分送ってすぐにUSDCに換えれば、
相場変動リスクを最小限に抑えた状態でDeFi運用や資産保全が可能になります。
逆に送金後すぐに両替せず放置すると、暴落の影響を受ける危険もあります。
この手順を覚えておけば、国内外問わず柔軟に資産を移動できるようになり、
例えば海外のNFTマーケットやブロックチェーンゲーム課金など、
国内では不可能なサービスにも即座に対応できます。
- 国内取引所で仮想通貨を購入し海外取引所へ送金
- 送金手数料は無料取引所かXRP利用で抑える
- 受け取った通貨をUSDTやUSDCに両替して活用
分散型取引所(DEX)での取引方法
DEX(分散型取引所)は中央管理者を介さず、
ウォレット同士で直接取引できる仕組みを持つ取引所です。
代表例はUniswapやPancakeSwapで、MetaMaskなどのウォレットを接続して利用します。
取引は24時間365日いつでも可能で、口座開設や本人確認は不要です。
具体的には、国内取引所でETHやBNBなど基軸通貨を購入し、
それをMetaMaskに送金。
Uniswapを開いてETH/USDCやBNB/BUSDのような取引ペアを選び、
希望数量を入力すれば即時に交換できます。
例えばETH 0.5枚をUSDCに交換すれば、
海外サービスでの利用やDeFi投資にそのまま使える形になります。
ただし、DEXではガス代(取引手数料)が必要で、
ネットワーク混雑時は数千円になる場合もあります。
また取引を間違えてスキャムトークンを購入するリスクもあるため、
公式リンクや信頼できる情報源からアクセスすることが重要です。
- ウォレット接続で口座不要・即取引可能
- 基軸通貨を送金後、ペア選択で瞬時交換
- ガス代やスキャムリスクへの注意が必要

DEXは自由度が高い反面、自己責任の世界。
事前に操作方法をテストしてから本格利用しましょう!
ほとんどの初心者にはウォレット不要とする現実的判断と、例外ケースまでを解説しており、ステーブルコインの運用前準備として有益です。
仮想通貨ウォレットは必要か?95%の初心者が知らない〝安全な資産保管の優先順位〟
知識武装してステーブルコインのチャンスを掴む
ステーブルコインは価格の安定性と利便性から、
多くの投資家やユーザーに活用されています。
しかし、正しい知識がなければリスクを見抜けず、
せっかくの機会を逃すどころか損失を被る可能性もあります。
この章では、リスクを最小限に抑えつつ長期的に活用するための心構えと実践ポイントを解説し、
あなたが仮想通貨市場で優位に立てる状態を目指します。
基礎知識で損失リスクを最小化する
ステーブルコインは一見安全そうに見えますが、
価格維持の仕組みや発行体の信頼性を知らずに使うのは非常に危険です。
例えば、2022年のUST崩壊では、多くの投資家が「1ドルと同じ価値を保つ」と信じ切ったまま資産を失いました。
このような事態を避けるためには、法定通貨担保型や暗号資産担保型などの種類ごとの特徴、担保率、規制状況を把握しておくことが重要です。
具体的には、取引所で購入する前にホワイトペーパーや発行体の公式情報を確認し、
担保資産の保有状況や監査体制をチェックします。
また、SNSやニュースで流れる噂やFUD(恐怖・不安・疑念)に流されず、
一次情報に基づいて判断する姿勢が欠かせません。
こうした基礎知識を持っておくことで、粗悪なコインを掴むリスクを大幅に減らすことができます。
例えば、USDCは発行体のCircle社が米国債や現金を担保に保有しており、
定期的な監査結果も公開されています。
一方で、無名のステーブルコインは担保資産の詳細が不明確な場合もあり、
突然価値を失う危険があります。
実際、過去には小規模プロジェクトのステーブルコインが担保不足で取引停止になった事例もあります。
このような具体例を知っておくだけでも、判断基準の精度は格段に上がります。
- 種類ごとの仕組みとリスクを理解して選ぶ
- 発行体の担保資産や監査情報を必ず確認
- 噂ではなく一次情報で判断する習慣を持つ
長期的に安全運用するための心得
ステーブルコインを長期的に活用するには、単に保有するだけでなく
「どこで・どう運用するか」という戦略が重要です。
例えば、利回りが高いDeFiプラットフォームに預ければ年利数%〜10%以上が狙えますが、
ハッキングやスマートコントラクトの脆弱性による資産流出リスクも伴います。
過去には大手DeFiサービスでもセキュリティ事故が発生し、
数億円規模の損失が出た事例があります。
安全運用の基本は「分散」と「定期チェック」です。
資産を複数のステーブルコインや複数の運用先に分け、
さらに定期的に担保状況や規制ニュースを確認します。
例えば、USDCとDAIを半分ずつ保有し、
一方は信頼性の高い中央集権型取引所に、
もう一方は監査済みのDeFiサービスに預けるなどが効果的です。
また、海外取引所を利用する場合は、利用規約や国別の規制変更にも敏感になりましょう。
さらに、利回りが極端に高い案件は注意が必要です。
特に年利数百%をうたうプロジェクトは、
持続性のないポンジスキームである可能性が高く、
途中で破綻して元本を失うリスクが大きいです。
短期的な利益に惑わされず、長期目線で安定的に運用できる選択肢を選びましょう。
- 資産を複数の通貨・運用先に分散する
- 担保状況や規制動向を定期的に確認する
- 高すぎる利回り案件には慎重になる

長く仮想通貨市場に残ることが勝ちへの近道!
短期の欲よりも生き残りを優先しよう。
まとめ:ステーブルコインを賢く使いこなすために
ステーブルコインは、価格の安定性とブロックチェーンの利便性を兼ね備えた、
新しい時代のお金のかたちです。
この記事では、その基本的な仕組みから、メリット・リスク、
種類ごとの特徴、そして実際の入手・活用方法までを網羅してきました。
ここで大切なのは、〝安全性は仕組みと選び方で決まる〟という視点です。
信頼できる発行元や透明性のあるプロジェクトを選び、
用途やリスク許容度に応じて賢く使い分けることで、
ステーブルコインは大きな味方になります。
また、資産を守りながら増やすためには、
分散や定期的なチェックといった地道な行動が欠かせません。
市場の変化に柔軟に対応できる知識と準備こそが、
長く仮想通貨市場で生き残る鍵です。
今あなたが手にしているのは、単なる金融ツールではなく、
世界中に瞬時で価値を届ける力です。
知識を武器に変え、その力を安全かつ戦略的に使いこなしていきましょう。
今日の一歩が、未来の大きな成果への道を切り拓きます。
仮想通貨で月5万円を目指す!初心者でも失敗しない投資資産運用の秘訣
しょーてぃさんのBrain「仮想通貨マスター講座~残業70時間でも仮想通貨で脱サラ!動画55本(6時間)」では、年500万円の収益化に成功した仮想通貨のノウハウが全て詰まっています。
- 「投資って何すればいいの?」がゼロになる、やるべき行動テンプレート
- 手を動かすだけで資産が増える、反復型ワーク式ステップ解説
- 投資初心者でも数字を伸ばせる〝キャッシュフロー改善ToDoリスト〟付き
- 学ぶ→実行→改善のループを回す〝成果構築ルーチン〟の設計図
- 〝行動できない人〟でも前に進める!仕組み化された実践チェックシート
- 【成果直結】投資成績を底上げする〝改善フィードバック表〟の中身とは?
- 投資に必要な〝数字思考〟を自然に身につけるテンプレート構造
- 投資リスクを抑える〝初動設計〟で失敗しない運用スタート術
- 何も知らなくてOK!仮想通貨ゼロスタートの完全ロードマップ
- 再現性100%のタスク分解術で、仮想通貨投資の迷いを一掃
- 知識だけで終わらない!〝成果が出る人〟だけが使うワークの正体
- FPに20万円払う必要なし!埋めるだけで完成する資産運用プランシート
- 【即金対応】10万円をノーリスクで作るセルフバック完全マニュアル
- 放置型運用も可!〝ほったらかしで資産が増える〟仕組みの作り方
- SNS初心者でも真似るだけ!仮想通貨副業テンプレート(X&note対応)
- 質問回数無制限!「わからない」が〝進まない理由〟にならない環境
- 復習効率を3倍に上げる!聞き流しOKな全講座音声再生リスト
- 知識ゼロからでも最短で稼げる〝初心者特化型10大特典〟つき
- 誰でも資産構築できる!全55本の超実践動画カリキュラムを完全公開
- 総スライド800枚超!6時間で資産運用の全体像がつかめる教材設計
しょーてぃさんのXでは、失敗しない仮想通貨の運用法が学べます。
フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。
しょーてぃさんのXはこちら。